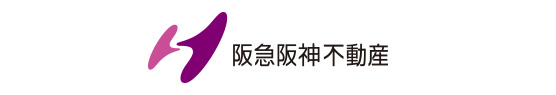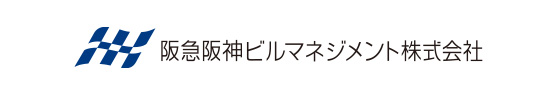部署の壁を越え、未来を塗り替える──関西ペイント、本社移転の背景

1918年の創業以来、総合塗料メーカーとして日本のみならず世界中に事業を展開してきた関西ペイント株式会社。2024年、長年拠点としてきた大阪・淀屋橋の自社ビルから、「大阪梅田ツインタワーズ・サウス」への本社移転という大きな節目を迎えました。
老朽化やBCP(事業継続計画)といった理由とともに、「働き方そのものを再定義し、企業を次のステージへと進めたい」という強い想いがありました。社員の連携を高め、組織の壁を取り払い、挑戦と成長を後押しするための移転。そこには関西ペイントらしい誠実な企業姿勢と、未来に向けた明確なビジョンがありました。
今回の移転をともに進めた関西ペイント株式会社の経営企画本部の皆さま、空間設計を担当したオカムラの皆さまに、移転の背景とプロセス、そしてこれからの展望についてお話を伺いました。
“変わらない日常”への違和感が、変革の起点に
本社移転を決断された背景を教えてください
水谷様(関西ペイント):以前の本社は、大阪・淀屋橋にある10階建ての自社ビルでした。部署ごとにフロアが分かれていて、基本的に日々の業務はそのフロアの中だけで完結していました。同じ会社にいながら、他部署の人と顔を合わせる機会がほとんどなく、すれ違っても挨拶を交わすことが少ない──そんな環境がいつの間にか日常になっていました。
加えて、建物自体の老朽化や、BCPの観点でも大きな不安を感じていました。実際に、ある日近隣で停電が発生した際には、非常用電源が十分に持たず、業務に影響が出るということもありました。
これらの経験を通じて、「このまま自社ビルを持ち続ける意味は本当にあるのだろうか」と考えるようになりました。場所を持ち続けることよりも、リモートワークの浸透などをはじめとした場所を選ばない、これからの時代に合った企業の在り方をどう実現するか。その視点に立って複数の選択肢を検討した結果、私たちは本社の移転という大きな決断を下しました。企業としてもう一段階、成長するために必要な一歩だったと思っています。
移転プロジェクトはどのように進められたのですか?
水谷様(関西ペイント):本社移転は、単なる場所の変更ではなく、関西ペイントにとって“企業文化そのものを刷新する挑戦”でした。重視されたのは「誰が決めるか」ではなく、「どう一緒に創るか」。その軸のもと、社内に立ち上がった移転プロジェクトチームには各部門から代表が参加し、議論を重ねながら空間の未来をかたちにしていきました。
情報共有も徹底して行い、イントラネットでの発信や現場ツアーを通じて、不安を期待に変えていきました。10ヶ月の全体スケジュールの中、全社員が“自分ごと”として考え抜いたことが、移転後のスムーズな働き方の定着の原動力となりました。
このオフィスは、与えられたものではなく、社員一人ひとりの意思が重なり合って生まれた空間です。共創を大切にする関西ペイントらしい本社移転でした。
企業の“らしさ”を空間に落とし込む挑戦

どのようなコンセプトのもとで設計されたのですか?
松本様(関西ペイント):今回の新オフィスの設計にあたって、私たちが掲げたコンセプトは「彩り・機能・保護」の3つです。これは、私たち関西ペイントが長年大切にしてきた価値観そのものであり、事業活動の本質でもあります。「彩り」は、私たちの原点。塗料を通じて社会に彩りをもたらし、「機能」は課題を解決する力を意味します。そして「保護」は、人や建物、環境を守るという塗料の根源的な使命です。
この3つを空間に落とし込むことで、私たちがどんな会社で、どこを目指しているのかを、オフィスに来てくださった方に伝えられる場所にしたいと考えました。
ステークホルダーとのコミュニケーションを大切に考え、エントランスやレセプションルームなどの共有空間には自社の塗料を使用しました。青・赤・黄の三原色をベースに、それぞれのスペースで異なる役割や印象を持たせるよう、カラーゾーニングにもこだわりました。空間ごとに、関西ペイントらしいストーリーが感じられることが理想でした。
森西様(オカムラ):関西ペイント様から「色にこだわりたい」という強いご要望をいただいてからは、我々としても“塗料メーカーとしてのらしさ”を、いかに空間として具現化するかに重きを置いて設計を進めました。
特に力を入れたのが、色の見え方に関する検証です。同じ塗料でも、照明の色温度や角度、素材との組み合わせによって、受ける印象がまったく異なります。ですので、色彩設計はもちろん、照明計画や素材の反射率まで含めて、関西ペイント様と密に連携しながら、細部まで調整を行いました。
「色の見え方ひとつにも妥協しない」──それが今回の設計の軸でした。単に“綺麗な色”を使うだけでなく、関西ペイントという企業のアイデンティティそのものを、空間全体で感じられるように仕上げています。
レイアウトやワークスタイル面での工夫を教えてください
水谷様(関西ペイント):「機能」の設計では、これまでオフィス内に存在していた“部署の壁”を物理的にも心理的にも取り払うことに挑みました。以前はフロアごとに部署が分かれていて、業務が完結する範囲も人間関係もその枠にとどまりがちでした。新オフィスでは、コーポレート部門をワンフロアに集約し、フリーアドレスを導入。部署や職種の垣根を越えた偶発的なコミュニケーションが自然に生まれるよう、導線やスペースの構成にも徹底的にこだわりました。
さらに、「集中」と「コラボレーション」を自由に切り替えられるように、多様な働き方に対応できる柔軟性を空間全体に持たせています。ひとりでじっくり考えたいときも、チームで活発に議論したいときも、自分にとってベストな環境を選択できる。そんな“自由と変化”を提供できるオフィスになっています。
そして、もう一つの重要なテーマが「保護」です。これは私たち関西ペイントが社会に提供している価値の根幹でもあります。建物や人、環境を守る──その使命を、オフィス空間にも明確に反映しました。
大阪梅田ツインタワーズ・サウスでは、有事の際にも最大72時間の電源供給が可能となっており、災害時の安全確保に関する機能も高い水準で整っています。今回の移転では、こうした高機能な建物特性を最大限に活かすことで、BCPの観点からも大幅な強化を図ることができました。
加えて、セキュリティ対策についても最新の仕組みを導入しています。オフィス全体のセキュリティレベルを分けることで社内の安全性と運用の柔軟性を両立しています。私たちが守るのは“モノ”だけではなく、ここで働く“人”の安全と信頼も含まれています。
オフィスは単に業務を行う場ではなく、企業としての姿勢や価値観を表現する“空間のメッセージ”だと考えています。この場所にいるだけで、関西ペイントがどんな会社で、どこを目指しているのかが伝わる――そんな空間を私たちは本気で目指しました。ブランドを感じさせる「象徴」であると同時に、未来への「意思表示」でもある。それがこの新本社です。
オフィスが変える、働き方と組織の関係


移転後、働き方にはどのような変化がありましたか?
松本様(関西ペイント):本社移転から1年。オフィス空間が変われば、働き方も変わるということを、私自身も実感しています。社内からは、「情報が得やすくなった」「相談しやすくなった」といった声が多く寄せられるようになりました。
以前のオフィスは部署ごとにフロアが分かれていて、業務も人間関係も“縦割り”になりやすい構造でした。それが新オフィスでは、コーポレート部門をワンフロアに集約したことで、物理的な距離が縮まり、自然と視線が交差し、言葉が交わされる環境になりました。意識的に話しかけるというよりも、「気がついたら話していた」というような、良い意味での“偶然性”が生まれていると感じています。
昇降式デスクは、デスクの高さを変えることで座るだけでなく立っても仕事ができる場所として、社員の間で非常に好評です。朝から真っ先に席が埋まってしまうほどの人気で、身体を動かすことで思考が活性化するという効果があり、社員の集中力向上にもつながっているように感じます。
また、移転当初はあまり活用されていなかったカフェスペースやラウンジも、今では部門を越えたコミュニケーションのハブとして機能しています。新たに導入した「顔写真付きプロフィールブック」も効果的で、名前と顔が一致することで声をかけやすくなり、関係構築のきっかけにもなっています。
もちろん、すべてが順風満帆というわけではありません。オープンな空間だからこそ、「他部署の声が気になる」「どこか落ち着かない」といった戸惑いの声もあります。ただ、それを問題として排除するのではなく、「私たち自身のマインドセットを見直すチャンス」として前向きに捉える雰囲気が社内にはあります。
私自身も「働きにくいと感じる課題は建物にあるのではなく、自分たちの内側にあるのではないか」と気づかされる場面もあり、自分たちの働き方や組織のあり方そのものを問い直すきっかけとなりました。――そうした姿勢こそが、今回の移転で得られた一番の成果なのかもしれません。
課題や見直しのポイントはありましたか?
松本様(関西ペイント):新たな挑戦は、すべてが完璧な状態から始まるわけではありません。オフィス移転も例外ではなく、理想と現実の間にあるギャップを一つひとつ丁寧に見つめ、改善のサイクルを回し続けてきました。
「声が気になる」「モニターの数が足りない」といった声に対しては、フロアの使い方を見直したり、モバイルバッテリーの追加、モニターの増設などを柔軟に進めています。
また、テレキューブに関しては、プライバシーを確保するために、ガラス面に目隠しフィルムを貼る配慮を実施。安心して会話ができる環境づくりを地道に続けています。一方で要望があっても、コミュニケーションが生まれやすい執務エリア内の打ち合わせ室については、要望をそのまま受けずあえて隠さない仕様を継続しています。
関西ペイントの本社移転は、“答えを押しつける”のではなく、“最適解を皆で探す”ことに重きを置いたプロジェクトでした。だからこそ、社員一人ひとりの声が、オフィスという場に息づいているのです。
その積み重ねこそが、これからの組織をさらに強くし、しなやかに育てていく原動力になるのではないでしょうか。
“空間が語る企業姿勢”──採用・未来戦略への影響

新オフィスは採用活動にも影響を与えましたか?
松本様(関西ペイント):はい、大きな影響がありました。移転後は、中途採用などの選考段階でオフィスを実際に見学していただく機会を設けるようになり、候補者から「この空間で働いてみたい」「企業の考え方が空間から伝わってくる」といった声が多く寄せられるようになりました。私たちにとって、オフィスは“働く場所”であると同時に、“無言のメッセージ”でもあります。企業文化や価値観は、言葉以上に空間から滲み出るものだと実感しています。
特に、部署間の垣根を取り払ったワンフロアのレイアウトや、カラーデザインにこだわったインテリアなど、「社員がどう働いているか」が一目で分かることで、入社前からリアルなイメージを持っていただけることが大きいですね。
こうした空間づくりが、採用だけでなく、入社後の馴染みやすさやその後の活躍にもつながっていると感じています。
私たちは「社員の成長が企業の成長に直結する」と考えています。オフィスをその成長の土壌とすることが、未来に向けた重要な投資だと確信しています。
今後の展望について教えてください
水谷様(関西ペイント):今回の本社移転は、私たちが取り組む「拠点再編プロジェクト」の第一ステップです。新大阪に続き東京といった国内主要拠点への展開を見据えながら、働く環境を全社的に最適化し、“挑戦と成長が連鎖する組織づくり”を進めていきます。
私たちは今「第18次中期経営計画」の中で、収益性と成長性の両立、そして経営基盤の強化を軸とした企業価値の最大化に取り組んでいます。その実現には、DX・グローバル連携・多様な人材活用といった要素が不可欠であり、それらを支える「場」としてのオフィスの重要性は、今後ますます高まると考えています。
この新しい本社がそうであるように、私たちのオフィスには「ブランド」「文化」「未来」が凝縮されているべきだと思います。ここに集う社員が、関西ペイントに関わることを誇りに思い、安心して挑戦できる。そんな環境を、国内外すべての拠点に広げていきたいですね。
私たちが目指しているのは、単なる“企業の成長”ではありません。「塗料で人を幸せにする」ことを共通ビジョンとする社員一人ひとりの挑戦が連鎖し、やがて社会や地球に価値を還元できるような企業になること。その土台を、オフィスという空間から築いていく──その意志が、この移転には込められています。
※掲載内容は取材当時のものです。